![14423955_902171336594382_1285139035_o[1]](http://ahirunoie.boot-boo.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/14423955_902171336594382_1285139035_o1.jpg)
ジャムは、水分を抱え込むことでその腐敗を遅らせるという糖分の特質を生かし、果物を砂糖煮にすることで長期保存を可能にした昔ながらの食品です。
あひるの家取り扱いのジャムの最大の特徴は、生産者が自ら育てた有機農産物や良質な原料を選び、果実のもつ自然な風味をそのままに加工していること。農産物への思い、その農産物の特長を最大限に生かそうとするジャム作りへの信念や独自のノウハウが一瓶、一瓶にとじこめられています。
ジャムは、パンに塗るだけでなくヨーグルトやアイスクリームのソース、ケーキに添えたり、肉に添えたり、調味料として料理に甘みを足すのにも使うことができます。また、お湯に溶けば、お茶としても楽しめます。
旬の美味しさギュッ!果物と洗双糖で作るジャム
自らの体験の中から生まれた“有機ブルーベリー”栽培
浜田さんは大学卒業後、約10年間にわたってネパールやラオスなどの農業開発事業に関わるかたわら、アフリカをはじめ世界各国をめぐり農業の現状にふれることで農薬や化学肥料を使った近代農業の危険性に気づきました。帰国後、栃木県佐野市で自然の生態系を生かした有機農業をはじめました。ブルーベリーの栽培は30数年になります。木のチップや籾殻、米ぬか、植物性堆肥のみで栽培しています。また、従来の品種に固執せずより美味しく日本の気候・風土にあった新たな品種の開発するため研究などもしています。
約1.2ヘクタールの畑には30年生の樹が約1,300本。収穫の時期が異なるハイブッシュ系、ラビットアイ系それぞれの品種を栽培。年間収穫量は約8トン、そのうち2.5トンがジャムの生産に使われます。熟し具合を見極めながら、一粒一粒手摘みで行うため収穫時期は毎日が時間との戦い。体力的にもハードです。毎年夏に手摘みした果実は生食として出荷されるもの以外はすぐに冷凍され、10月~翌年5月くらいまで大切にジャム作りに使われます。
果実の特性を熟知した生産農家が作り出す
つぶつぶ感のある日本一のブルベリージャムづくり
ジャム製造を始めたきっかけは「ブルーベリーを知り尽くした生産者が作れば日本一のジャムが作れる」との考えから。
一釜で30kg、約230瓶つくります。30kgのうち、15kgが皮が柔らかくとろ味が出るクエン酸が主体のハイブッシュ系、5kgがコハク酸(アントシアニン含)が主体のラビットアイ系ホームベル、10kgがラビットアイ系ティフブルーを使用。ハーバード種は、粒のまま釜にラビットアイ系ホームベルは種が入ると舌ざわりが悪くなるので機械で種を除き、半分はそのまま、残りの半分をクラッシュして釜に。ラビットアイ系ティフブルーは圧力釜で煮込んで裏ごし。それぞれに品種ごとのおいしさを生かすよう下ごしらえをした後、合わせ、煮込みます。洗双糖を数回に分けて加え、撹拌しながら約1時間半煮込む。火を止めるタイミングもおいしさのポイント。旨味、果実のもつ機能性のバランスまでを考えてつくるジャムづくりは大変奥深い作業。熱いままビン詰めし、95度の熱湯に1時間漬けて脱気・殺菌して出来あがりです。
【ハマダさんちのブルーベリージャム】 140g 650円
有機ブルーベリーと洗双糖のみを使用し、果実の特性を熟知した生産農家が作りました。じっくり時間をかけて丁寧に煮詰めた果肉つぶつぶ感のあるソースタイプ。酸味と甘さがほど良くヨーグルトとの相性は抜群。糖度は46度とおさえめです。ブルーベリーは眼精疲労にも効果が期待できます。
ブルーベリー(Blueberry)は、ツツジ科スノキ属に分類される北米原産の低木性果樹です。熟すにつれ果実が青く染まることからブルーベリーと呼ばれています。
ブルーベリーの濃い青紫色はアントシアニン色素と呼ばれ、水溶性の色素です。このアントシアニン色素が、目の網膜にあるロドプシンの再合成を助ける働きがあるため眼精疲労に効果的な果実といわれています。「アントシアニン」はブルーベリーの皮に多く含まれています。ジャムは皮も実も丸ごと使っていますから、目にいいとされる成分がたっぷり入っているわけです。ブルーベリーには他にも糖尿病や生活習慣病、ガンを引き起こす活性酸素を抑制する抗酸化力があるともいわれ、その抑制効果は緑茶に含まれるカテキンや玉ねぎに含まれるケルセチンにも匹敵するといわれています。
放射性物質[不検出]検出限界値1ベクレル/kg
地元栃木の契約農家が栽培した新鮮いちごを使用
冬の太陽光を利用したハウスで品種特徴に合せた温度管理を行いながら栽培し、いちご本来の香りと食味と引き出します。いちごジャムに使われるいちごの収穫は11月~5月下旬。収穫したてのいちごはヘタを取り洗浄後すぐに冷凍します。鮮度のよい原料を冷凍保存することで、年間を通して一定の品質を保ったジャムをつくることができます。
大粒果肉ゴロゴロ、満足感のあるプレザージャム
果実を潰してペースト状にしてしまうのではなく、果実の形を残したプレザータイプのジャムづくりをしています。一釜で約72kgのいちごと18kgの洗双糖、約300mlのレモン果汁が使われ、約240本のジャムが出来あがります。
冷凍された原料いちごによって釜火の強さ加減や攪拌具合は毎回違います。【いちごジャム】はミネラルを含んだ洗双糖を使用するため、一般的なものに比べ、煮詰めると自然に赤黒くなります。色つやをよくするためにレモン果汁(クエン酸)を加えます。このレモン果汁も直前に手搾りした新鮮なものを使用します。煮込むにつれいちごの実から汁とともに灰汁がでますが、これも丁寧に目の細かい網のようなものでこまめにすくいます。撹拌をしすぎるとせっかくのいちごの粒が潰れてしまうため必要以上に撹拌はしません。状態を見極めながら煮熟時間や洗双糖を加えるタイミングを見計らい家庭でつくるように丁寧に仕上げていきます。
最後の仕上げ、熱いジャムを熱い瓶に詰める
ジャムは空気中の酸素に触れているだけで酸化が進んでしまうため、煮上がったジャムは熱いうちに、瓶詰めします。充填前の瓶も一つ一つ慎重に目視と触診をします。ジャム充填後のふた締めも大変な作業のひとつです。出来たてのジャムはとても熱く厚手の手袋をしていても熱が伝わっていきます。瓶詰め後、熱湯90℃で20分の脱気殺菌をして出来あがりです。
【ポラーノ手作り苺ジャム】 190g 500円
いちごと洗双糖、国産レモン果汁のみで作ったシンプルないちごジャムです。基本に忠実に手間ひまかけて作るジャムは、なんだか懐かしくなる味です。いちごの粒の食感、程良い酸味と甘みの絶妙なバランスをお楽しみいただけます。糖度は60度です。
放射性物質[不検出]検出限界値1ベクレル/kg
素材の味を最大限に生かしたジャム、マーマレード
果実の原型をとどめないほどに煮詰めてゼリー状にした食品を、ジャム(Jam)といいますが、果実などを潰さずに原形が6割り程度残っているものをプレザージャム(Preserve Jam)といいます。また、柑橘類を主原料とし、その果汁だけでなく果皮切片を混ぜてゼリー化したものをマーマレード(Marmalade)といいます。
【りんごジャム】 140g 480円
青森の新農業研究会のりんごを使っています。完熟したりんごとミネラルを含んだ洗双糖で、風味よく仕上げています。糖度は45度と控えめで、りんごの風味が口の中に広がります。
放射性物質[不検出]検出限界値1ベクレル/kg
【桑の実ジャム】 150g 650円
島根産の有機桑の実を丸のままと甜菜糖を使用して作られた珍しいジャムです。見た目はフランボワーズ(木イチゴ)のようですが、甘味の酸味のバランスが良い上品な味。アントシアニンや亜鉛が含まれ、疲労回復効果も期待できます。糖度は60度です。
【手づくり甘夏マーマレード】 155g 500円
水は一切加えず、津奈木甘夏生産者の会の有機甘夏と洗双糖のみで仕上げました。有機甘夏の内袋を丁寧に取り除くことで酸味のないおいしいマーマレードになっています。パンやスコーン、ヨーグルトはもちろん、肉料理などにもどうぞ。糖度は48度です。

![14502913_1761605140769004_2841602458918985888_n[1]](http://ahirunoie.boot-boo.org/blog/wp-content/uploads/2016/10/14502913_1761605140769004_2841602458918985888_n1.jpg)
![14550493_906736559471193_1862265680_o[1]](http://ahirunoie.boot-boo.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/14550493_906736559471193_1862265680_o1.jpg)
![14513757_906129132865269_2031169377_o[1]](http://ahirunoie.boot-boo.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/14513757_906129132865269_2031169377_o1.jpg)

![14456776_904887709656078_276199055_o[1]](http://ahirunoie.boot-boo.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/14456776_904887709656078_276199055_o1.jpg)

![14423955_902171336594382_1285139035_o[1]](http://ahirunoie.boot-boo.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/14423955_902171336594382_1285139035_o1.jpg)
![14424233_902158763262306_1104707629_o[1]](http://ahirunoie.boot-boo.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/14424233_902158763262306_1104707629_o1.jpg)
![14407960_901467889998060_1564628103_o[1]](http://ahirunoie.boot-boo.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/14407960_901467889998060_1564628103_o1.jpg)

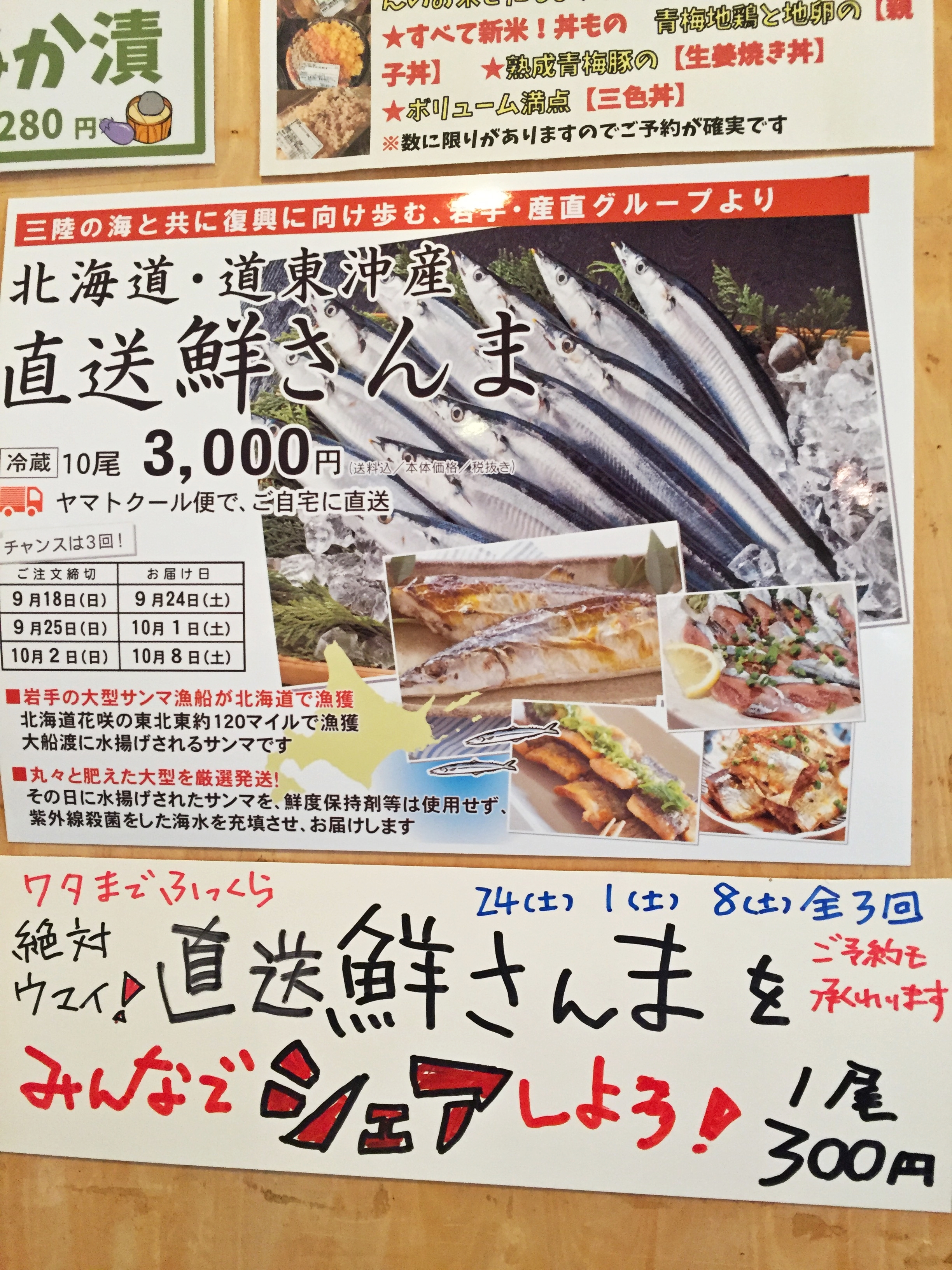
![sanma111[1]](http://ahirunoie.boot-boo.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/sanma1111.jpg)